「高配当ETFは魅力的だけど、デメリットもあるらしい…」
そう聞くと不安になるかもしれません。
でも実は、その“デメリット”を正しく理解すれば、むしろ安心して投資を続けるポイントになります。
この記事では、高配当ETFを検討するうえで知っておきたい注意点を、初心者でもわかりやすく解説します。
1. 為替リスク
デメリット
高配当ETFはドル建ての商品なので、円高になると配当が減ってしまうことがあります。
例えば、1ドル=150円の時に10ドルの配当を受け取ると1,500円ですが、円高で1ドル=120円になると1,200円に。
同じ10ドルでも、日本円に直すと受け取れる額が少なくなるわけです。
実際のイメージ
- 円高(1ドル120円) → 配当は減る
- 円安(1ドル150円) → 配当は増える
メリットに変わるポイント
裏を返せば、円安のときは配当金が増えるということ。
さらに、円だけに資産を持っていると、将来インフレで円の価値が下がった時に生活が苦しくなる可能性があります。
ドル建てのETFを持っていることで、「通貨分散」=資産を円とドルに分けるリスクヘッジが自然にできるんです。
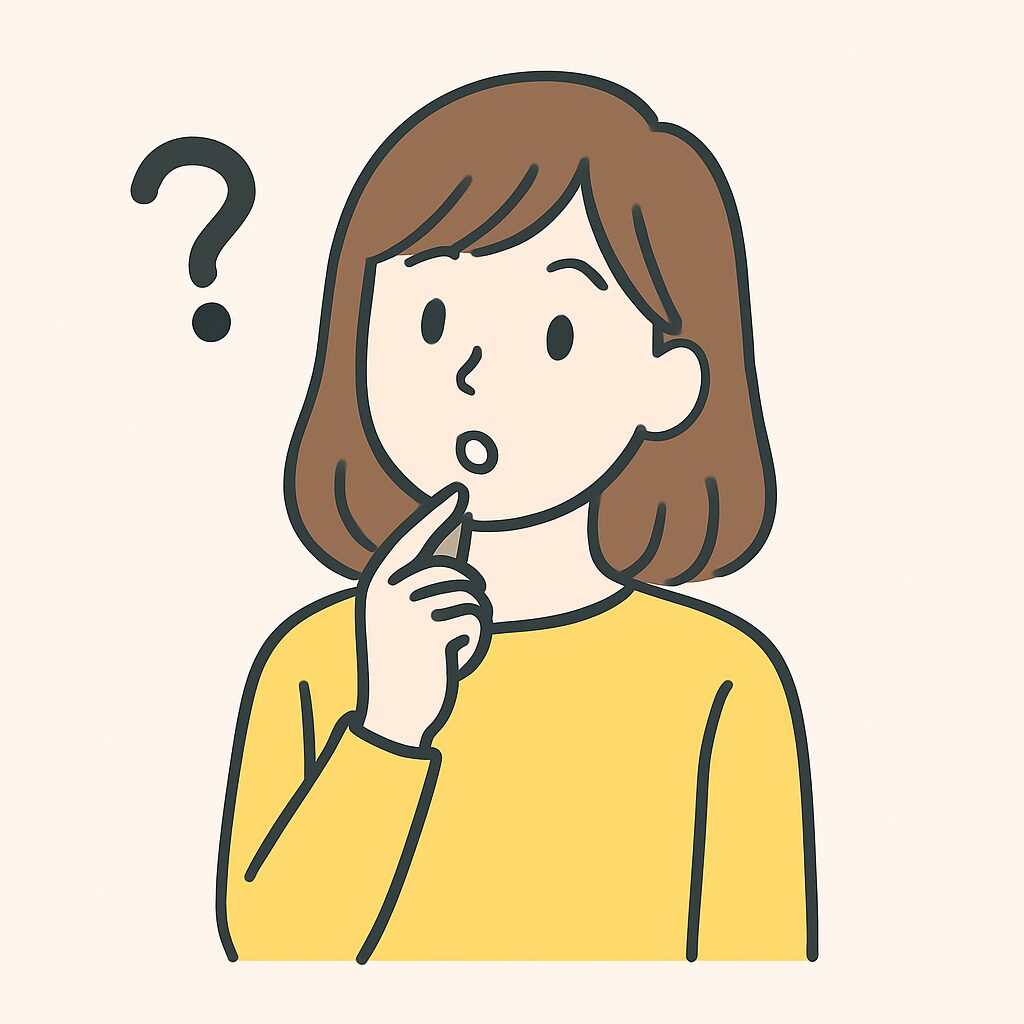
円高になったら損するだけかと思った…

むしろドルでも資産を持つことで、日本円の価値が下がった時に守ってくれるんだよ
2. 減配リスク
デメリット
高配当ETFも「景気の影響」を受けるので、配当が減る(減配する)可能性があります。
例えば不況になると、企業の利益が落ち込み、支払える配当金が少なくなることも。
「せっかく投資したのに、配当が減ったら意味ないのでは?」と不安になる人もいるでしょう。
実際のイメージ
- 個別株:その会社が不調だと一気に減配や無配になることもある
- ETF:数百社に分散しているので、1社や数社が不調でも大きな影響は少ない
メリットに変わるポイント
VYMのような高配当ETFは、分散投資の仕組みで作られています。
例えばVYMなら約400銘柄に投資しているため、1社が減配しても他の企業がカバー。
結果的に、個別株よりも安定して配当を受け取りやすいのです。
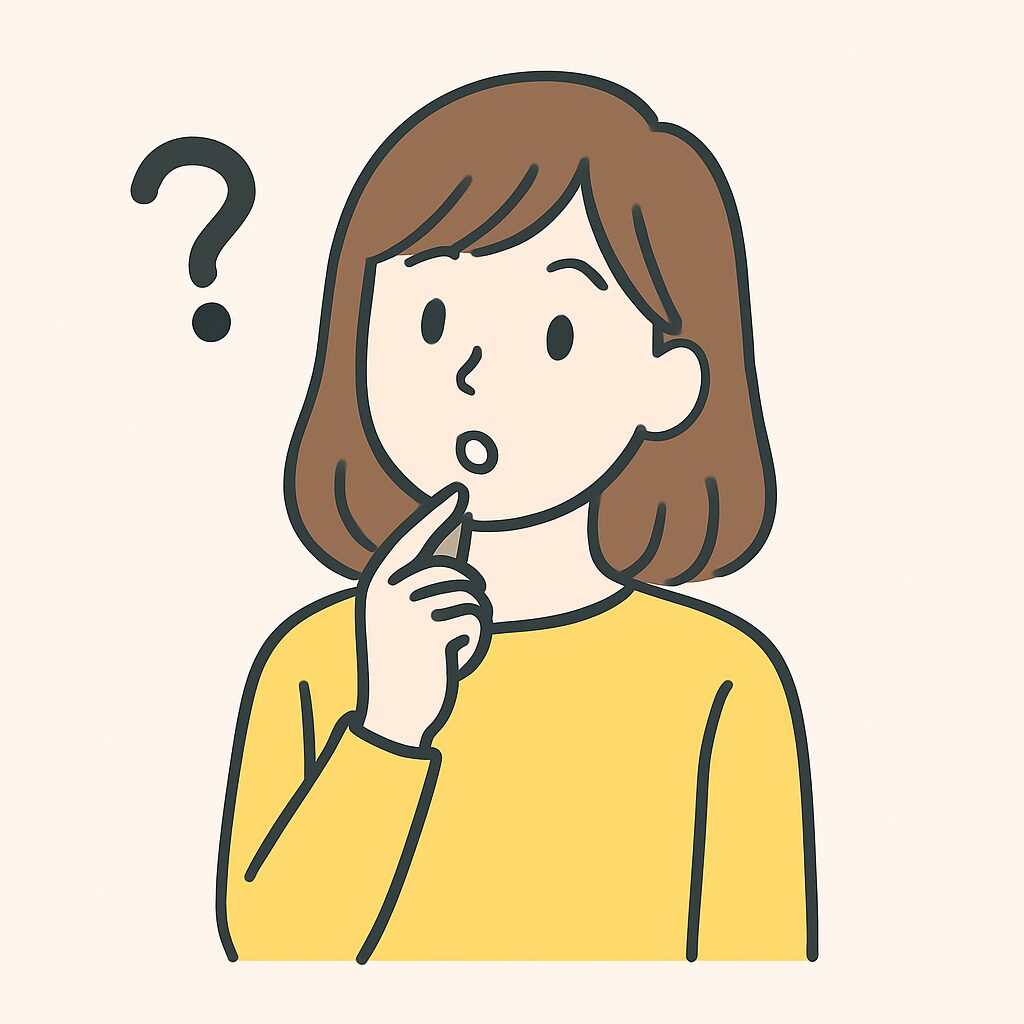
減配があるなら不安だな…

逆にETFなら“リスクを分散してくれてる”から、1社に頼るより安心できるんだよ
3. 株価下落リスク
デメリット
高配当ETFも株式なので、株価が下がると含み損が出ることがあります。
「せっかく投資したのに、資産が目減りしたら意味ないのでは?」と不安になるかもしれません。
実際のイメージ
- 株価が100ドル→80ドルに下がると、一時的に20%の含み損
- 含み損を見て焦って売却すると、損失が確定してしまう
メリットに変わるポイント
下落局面は、実は買い増しのチャンスです。
株価が下がる=同じ投資額でより多くの株数を買えるということ。
さらに高配当ETFは、株価が下がっても配当自体は出続けるので、利回りがUPする効果があります。
長期で見れば景気は循環し、株価も回復することが多いので、下落はむしろ将来のリターンを大きくする種まきになるんです。
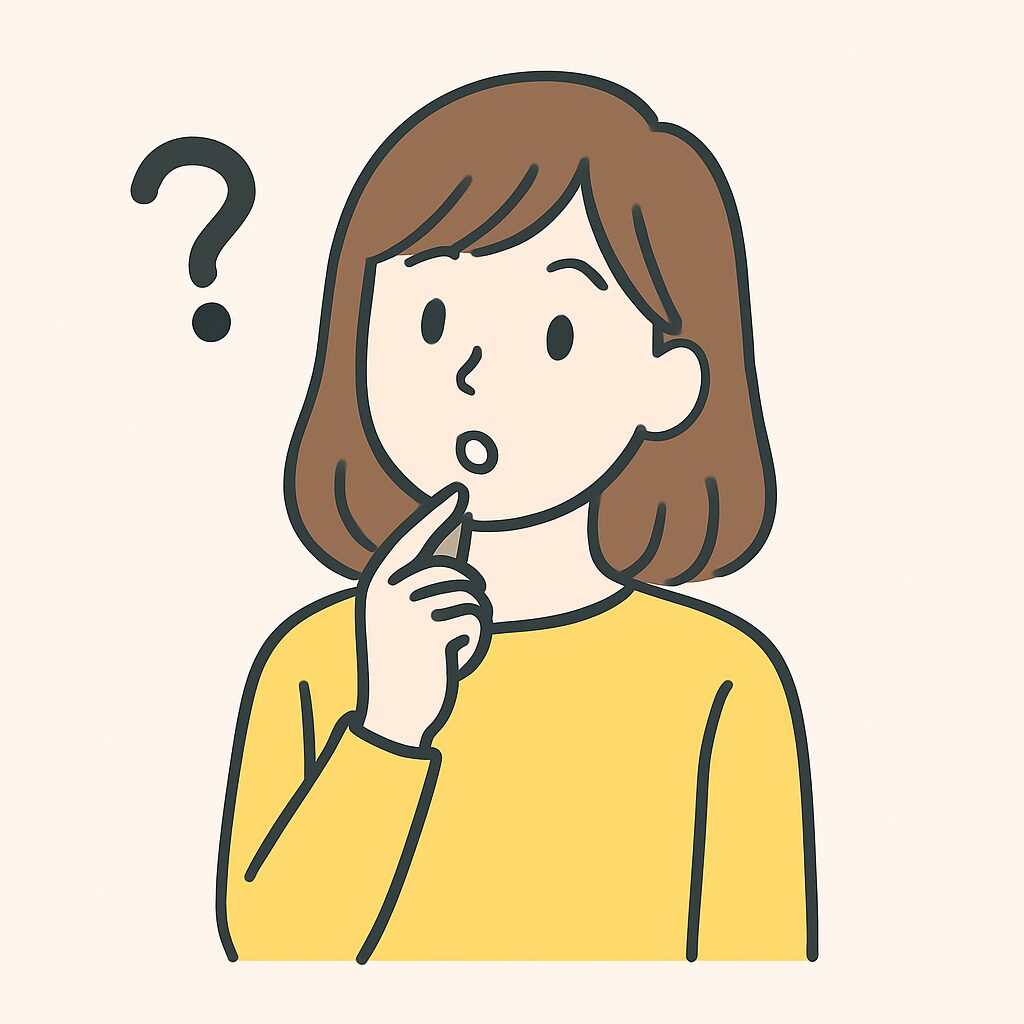
株価が下がるのは怖いけど…

高配当株投資は“売らずに持ち続ける”のが前提。だから下がった時こそ買い増しのチャンスなんだ。安く仕込めれば、その後の配当利回りはもっと大きくなるよ
4. 米国課税10%
デメリット
高配当ETFはアメリカ市場の商品なので、配当金に米国で10%の源泉徴収がかかります。
「NISAなのに課税されるの?」とガッカリする人もいるかもしれません。
実際のイメージ
- VYMから100ドルの配当が出た場合 → 米国課税10%で90ドルになる
- その90ドルが日本に入ってくる仕組み
メリットに変わるポイント
確かに米国課税10%は残りますが、日本の20%課税がゼロになるのが新NISAの大きな強みです。
もし通常口座で受け取れば「米国10%+日本20%」で実質28%も課税されます。
新NISAを使えば、それが「米国10%だけ」で済むので、国内株よりも手元に残るお金は多いんです。
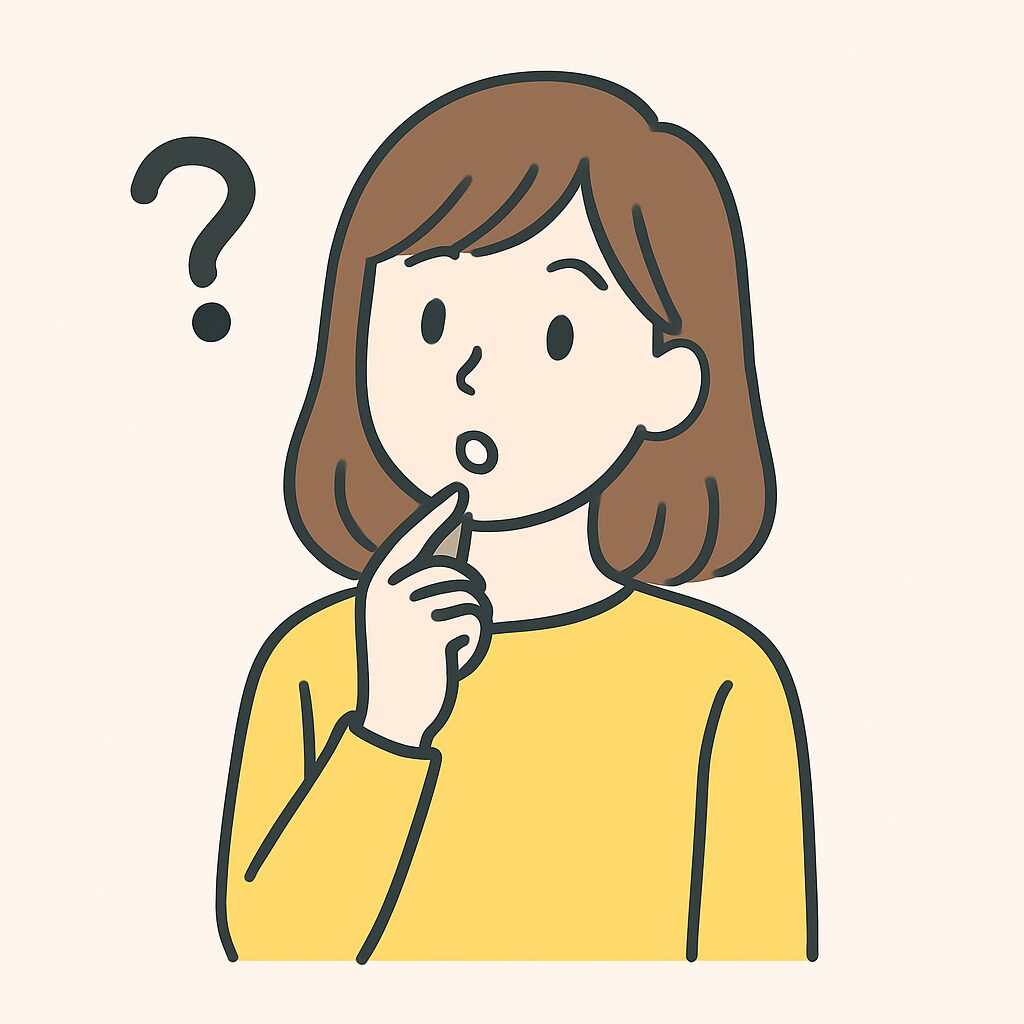
NISAでも完全に非課税じゃないんだね

でも日本の20%が免除されるから、トータルでは国内株よりお得。だからこそ新NISAとVYMの組み合わせは強いんだよ
まとめ
高配当ETFには「為替」「減配」「株価下落」「米国課税」といった注意点があります。
でも、それらは“失敗の原因”ではなく、知っていれば武器になる特徴です。
Z世代のうちから理解して投資を始めれば、
- 円だけに頼らない「通貨分散」
- 個別株より安定した配当
- 下落局面での買い増しチャンス
- 国内株より有利な非課税メリット
を活かして、将来の不労所得づくりに大きなアドバンテージを得られます。
👉 初心者におすすめ!高配当ETFの王道「VYM」解説はこちら
👉 新NISAを使ってVYMを買うメリットを解説した記事はこちら
当ブログは一次情報に基づいて執筆しています
👉 参考・引用サイト一覧はこちら


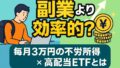

コメント